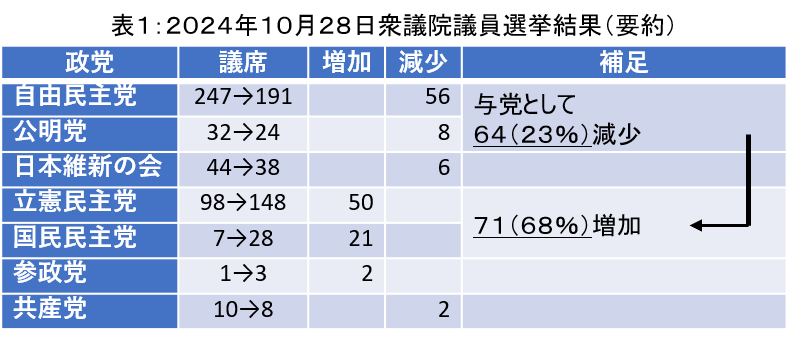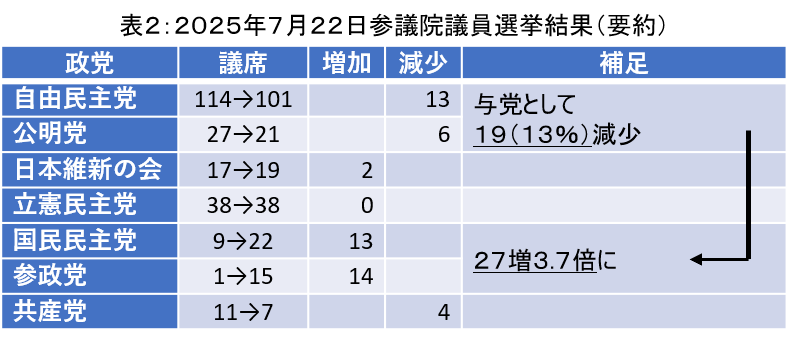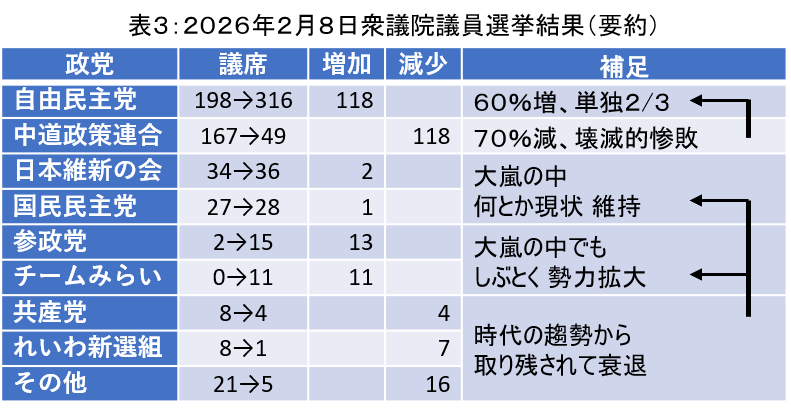11月7日予算委員会
今回の事件の発端となった高市首相発言は、11月7日の衆議院予算委員会における立憲民主党岡田克也氏との質疑応答の中で飛び出した。このQ&Aの詳細については、ジャーナリストで現代ビジネス編集次長の近藤大介氏の記事から該当する箇所を抜粋して引用する。(資料1参照)
<岡田:存立危機事態について、麻生さんも安倍さんも軽々しく扱っている。存立危機事態で武力行使すれば反撃も受ける。それを避けるのが政治家の役割だ。>
<高市:あらゆる事態、最悪の事態を想定しておくことは非常に重要だと思う。台湾を中国の支配下に置くために、どういう手段を使うか。単なるシーレーンの封鎖であるかもしれない。武力行使であるかもしれない。ニセ情報であるかもしれない。だけれども、戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、まあこれは、どう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考える。実際に発生した個別具体的な事情に応じて、政府が全ての事情を総合的に判断するということだ。実際に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高い。法律の条文通りであると思っている。>
<岡田:武力行使が誰に発生することを言っているのか? もっと明確にしないといけない。・・・(台湾からの)大量の避難民、数十万人、数百万人が発生する。そういった人々を受け入れる必要がある。そういう時に、日本が武力行使をしていたら、極めて差し障りが出てしまう可能性が高い。存立危機事態、武力行使は慎重に考えねばならない。余りに軽々しく言っていないか?>
<高市:存立危機事態の認定に際しては、個別具体的な状況に則して、主に攻撃国の意志・能力・事態の規模・対応などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻さ、重大性などから判断すべきものと考えている。政府として、持ちうる全ての情報を用いて判断する。これは当然のことと思っている。
この首相答弁のどこが問題だというのだろうか。「戦艦」という用語が既に使われていないこと以外に、不適切な箇所は何もない。
存立危機事態
初めに存立危機事態というのは、「①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、②これにより我が国の存立が脅かされ、③国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明確な危険がある事態」と定義されている。 そして存立危機事態は、定義に書き込まれた三つの要件①~③の全てが満たされ、閣議決定され、国会の承認を得て発動される。
元海将で、金沢工業大学大学院教授の伊藤俊幸氏は、三つの要件を満たすには情報に基づく総合的判断が必要であり、更にその後二つのステップを経て初めて事態認定されるもので、「要件に該当する可能性がある」という首相答弁は「法的一般論」を述べたに過ぎないと指摘する。(資料2参照)全くそのとおりだ。
中国が大騒ぎしたことを受けて、日本側からも踏み込み過ぎという報道と記事が目立った。高市首相が「言わなくてもいいことを勇み足で喋ってしまったから、中国を過剰反応させた。軽率だった。」という論調だ。安倍総理が常に慎重に言葉を選んで中国抑止の発言をしてきたのと比べて、軽率ではなかったかという批評である。
本当にそうだろうか。伊藤教授は資料2の中で、「首相が可能性を語る意義は、リスクを国民と共有し国の判断基準を透明化するためにある」と述べている。現在の国際情勢を概観すれば、ロシアがウクライナに軍事侵攻して、中国がロシアの戦争経済を支え、北朝鮮が戦場に武器と兵士を送って参戦している。イスラエルとパレスチナ・ゲリラとの戦闘が拡大し、世界が戦争モードへシフトした感がある中で、中国が台湾侵攻に踏み切る蓋然性が高まっている。この国際情勢下で首相が存立危機事態の要件について踏み込んだ答弁することは、むしろ時機を得た行動と見るべきではないだろうか。
近藤大介氏は資料1の中で、「岡田克也氏のイチャモン質問」と書いているが、現実の国際情勢と対峙して、国民に対する安心安全の全責任を背負っている高市首相に対して、自らは評論家席に陣取って揚げ足取りの質問をしている岡田氏の方が余程無責任であると言わざるを得ない。「立憲民主党というのはどこの国の政党なんだ」という声がそれを象徴している。
このように安全保障の危機が高まっている国際情勢において、ロジカルにはっきりモノを言う高市首相に対する国民の支持率は70%超を維持している。国民の方が敏感に危機を感じ取りリアルポリティクスを支持している事実を、野党政治家は軽視すべきではないだろう。
中国がとった威圧行動
何れにしても中国の反応は相当に常軌を逸したものだった。中国がとった威圧行動を列挙すると、次のとおりである。
11月8日:中国駐大阪総領事がXに書き込み
14日:日本への渡航自粛を指示
16日:日本への留学再考を注意喚起
17日:各地で予定されていた日中友好行事を取りやめ
18日:報道官、高市首相の非核三原則発言に抗議
19日:18日に北京で日中局長級会議が開催され、会議終了後、ポケットに両手を突っ込んだ中国の局長に対し金井局長が頭を下げているように見える動画がSNSに拡散
18日:国連でも対日批判を展開
19日:日本産水産物を禁輸
20日:スパイ摘発強化を示唆
吹き飛んだ日中首脳会談の成果
10月31日に開催された日中首脳会談において、習近平国家主席は「五つのコンセンサス」をしっかりと守り、実施することを強調したばかりだった。ちなみに「五つのコンセンサス」とは次のとおりである。(資料3から引用)
1.「戦略的互恵関係を全面的に推進し、相互パートナーシップ、相互に脅威とならない、歴史を鏡に未来を向く、などの政治的コンセンサスをしっかり実施する・・・」
2.「ウィンウィン協力を堅持する・・・」
3.「人々の心の交流を促進する・・・」
4.「多国間協力を強化する・・・」
5.「意見の相違を適切に管理する。大局を見据え、共通点を求め相違点を認め、一致点を集め対立を和らげ、矛盾や対立が両国関係を定義づけることを回避する。」
このコンセンサスを相互に再確認してから、僅か1週間後に中国は相次ぐ威圧行動をとったのだった。格調高く歌い上げた戦略的互恵関係だったが、僅か1週間で脆くも崩れ去ろうとしている。
中国側が態度を硬化した原因
一体中国側がここまで過激に反応したのは何故だろうか。多くの識者がさまざまな視点から論評しており、論点が既に出尽くした感がある。中国側が何故態度を硬化させたのかについて、ジャーナリストの青山和弘氏が分かり易く解説しているので、以下に要点を紹介する。(資料4参照)
1)日本は専守防衛の国だから、自分から攻撃することはできない。相手からの攻撃に対し反撃するにしても、反撃の根拠となる事態の認定が必要になる。存立危機事態は自分は攻撃されていないが、集団的自衛権を行使してどういう時に自衛隊が防衛出動できるのかを決めるという、極めて複雑な問題である。
2)もし台湾に米軍が来て中国が武力を行使すれば、台湾で米中戦争が起きるため、我が国の存立が脅かされる。台湾から約100km東に位置する与那国島に戦火が及ぶかも知れないし、中国が在日米軍基地を攻撃対象にするかもしれない。そうなれば日本にも明白な危険が及ぶ事態となって、存立危機事態になり得る。
3)高市首相は、ここまでエスカレートしたら確かに存立危機事態になり得るよね、という一般的な解釈として常識的なことを言ったのだが、これまでここまではっきり発言した総理は過去にいなかったことから、中国は「台湾有事に日本が自衛隊を出してくるのか、ふざけるな」という話になってしまった。
台湾を巡る国際情勢の変化
評論家で千代田区議会議員の白川司氏は、「中国の過激な反応の原因は、高市発言よりも大阪総領事の暴言に対する日本側の反応が大きく、削除しても収まらなかったため、中国政府として引っ込みがつかなくなったことにある。」とみる。(資料5参照)
白川氏は今回の過激な反応は三つの要因が重なったために起きたと指摘する。即ち米中戦略環境の悪化と、中国経済の停滞と、中国国内政治の力学の三つだ。
アメリカはそれまでの台湾政策を転換して、「台湾を実質的な国家に昇格させる」方向に舵を切った。アメリカ議会では台湾関連法案が相次いで提出され、上院では『台湾保障実行法案』が可決された。そこには従来の台湾政府との公的接触制限を見直す項目が含まれている。さらに上院外交委員会は台湾の地位について「台湾住民の意思に基づかない一方的な変更に反対する」立場を鮮明にした。
中国経済の停滞は言うまでもないだろう。国内政治力学とは、台湾政策は中国共産党にとって権力の正統性を担保する核心的利益であるために、弱腰を見せることはできず、常にファイティングポーズをとり続ける他ないということだ。
これら三つの要因に加えて日本では高市政権が誕生して、中国に対する日本側の体制が変化している。少なくても中国にはそう見えるに違いない。何故なら高市首相の閣僚人事が親中国から親台湾にシフトしたことと、他一つは日中関係のパイプ役を果たしてきた公明党が連立政権から離脱したことだ。何れも中国にとって重大事件だったのである。
中国側のお家事情
中国側に深刻なお家事情があると分析するのは近藤大介氏である。お家事情として近藤氏は10項目挙げているが、中でも重要な要点について紹介する。(資料1参照)
第1は、台湾有事の際の日本の立ち位置に対する誤解だ。ウクライナ戦争におけるロシアとドイツの関係は、台湾有事における中国と日本の関係と相似形だと中国の識者は考える。即ちドイツはウクライナを支援するがロシアとは戦火を交えていないし、ロシアもドイツを攻撃する気はない。それと同じで、台湾有事が起きれば日本は台湾を支援するだろうが中国と戦火は交えない。中国も日本を叩いたりはしない。それが高市発言で日本が台湾有事を殊更に強調したものだから、「日本はウクライナになるつもりか」と誤解し仰天したというのだ。
第2は、存立危機事態に対する誤解である。前述したように、存立危機事態の三要件の一つは「日本と密接な関係にある他国」に対し武力攻撃が発生することである。ここで「他国」は特定されておらず、日本にとっては当然他国=アメリカで集団的自衛権の発動を想定するのだが、中国は他国に台湾が含まれると誤解したというものだ。つまり、ひとたび台湾有事が起きれば、日本が参戦してくると高市首相が明言したと受け止めたことによる。もっとも現在では台湾は国として認められていないのだから、「他国」が台湾を含むという解釈は成り立たないのだが。
第3は、高市政権が誕生したときに習近平主席は祝辞を送らなかったが、これは台湾の頼清徳総統を支援する政権が日本に誕生したと中国が受け止めたからだ。
第4は、習近平主席は「上から目線」で見ていて、今では中国が兄貴分、日本が弟分の関係にしてゆくことを目論んでいるが、高市政権は一々「反抗」しており、それが歯がゆいというものだ。
第5に、10月末に日中首脳会談が開催されたが、習近平主席は触れて欲しくない点を高市首相からズケズケと指摘されて、面子を潰される展開となった。これは首脳会談をセットした中国外交部(トップは王毅外相)の大失態であり、「悪いのは日本だ」と責任回避を図ろうとした。
「一つの中国」問題の再燃
前駐オーストラリア特命全権大使で外交評論家の山上信吾氏は、日中間で「一つの中国」問題が再燃したとみる。(資料6参照)
1952年に発効したサンフランシスコ平和条約以降、「一つの中国」は中国側の主張であって、日本政府として受け入れたことは一度もない。ウクライナ戦争以降、台湾有事の蓋然性が高まっているが、高市首相が「存立危機事態」について一般論の答弁をしたことに噛みついて、中国は「高市政権が一つの中国問題に首を突っ込んできた」と解釈した可能性が高いというものだ。
習近平が直面するジレンマ
習近平主席は本当は高市発言に頭を抱え、ジレンマに直面しているという見方がある。ジャーナリストの石森巌氏は、「中国側の強硬姿勢には、いささか腰の引けた奇妙なチグハグさが随所に垣間見える。」と指摘する。(資料7参照)
「腰が引けている」第1の理由はヒステリックな反発の狼煙を挙げているのは取り巻き幹部ばかりで、習近平主席本人は一言も発言していないことだ。第2の理由は日本に対し威圧をかければ、それでなくても大失速に向かっている中国経済がさらに悪化する可能性が高まることだ。
中国では今、経済情勢が急激に悪化している。不動産バブル崩壊に起因する巨額な不良債権問題が深刻化して、経済が急失速する中、失業者が溢れ、若者には就職先がない。そこにトランプ大統領による関税制裁が襲いかかった。ここで更に日本との関係が冷え込めば、戦略的互恵関係を梃に経済を立て直したいという目論見が水泡に帰してしまうという訳だ。
東京財団政策研究所主席研究員の柯隆氏は、悪化した日中関係について次のように分析している(資料8参照)
「状況は複雑化しているが、日中双方とも関係をこれ以上悪化させたくないことが明らかだ。中国がとった制裁措置は何れも日本に実害の小さなものばかりで、中国では半日デモも起きておらず、日本製品の不買運動も起きていない。」
「反日デモが起きないのは、中国経済が低迷しており若者の失業率が高止まりしているからだ。更に現在はトランプ関税戦争の渦中にあり、このタイミングで大規模な反日デモが起きれば、日本企業の中国離れが加速して中国経済にさらに深刻なダメージを与えることになる。しかも中国社会で不満が溜まっており、反日デモが反政府デモに発展してしまう恐れがある。」
「日本製品の不買が呼び掛けられていないのは、日本製品のコアな部品は日本から輸入され中国でアセンブリが行われているので、不買運動が起きれば、結果的に中国企業を制裁することになるからだ。」
事態を悪化させた中国総領事の暴言
高市首相の発言に関わる中国の反応よりも、日本が警戒心を最高度に高めたのは駐大阪の薛剣中国総領事によるXへの投稿記事だった。「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」と書き込んだメッセージは、ジャーナリストで産経新聞論説委員長を務めた乾正人氏が言うように、「高市首相殺害を予告する脅迫文」と認定されてもおかしくない。政治的判断を別とすれば、毅然と「ペルソナ・ノン・グラータ(ラテン語で、好ましからざる人物)」指名して国外追放すべき悪行である。(資料9参照)
総領事によるこの記事は高市首相答弁翌日の11月8日土曜夜に投稿されて、投降後に削除されている。ここに謎が二つある。一つは総領事個人の行動か、それとも中国政府の指示または了解に基づく行動かであり、他一つは感情的な反発か、それとも計算された意図的行動かだ。
前述の白川司氏は、次のように分析する。「注意すべきは、中国政府が激しい口調で制裁をちらつかせながら答弁の撤回を言い出したのは、大阪総領事が高市首相に対する暴言を投稿し、削除しても日本国内からの批判が集中した後である点だ。これは今回の中国政府の過剰な反応が、高市首相の答弁自体より大阪総領事の暴言問題で引っ込みがつかなくなったからだと考えられる。」(資料5参照)
この総領事は2021年夏に着任して以来、SNSで過激な発言を繰り返してきたいわく付きの「戦狼外交官」だったという。高市首相発言は法的に正当な答弁であり、<論理的に反論できないから暴言で威嚇した>と考えられる。
在日台湾人団体が出した共同声明には「中華人民共和国は台湾を支配したことは一日もなく、中国が台湾の主権を主張したいのであれば、その根拠を明確にし、台湾人の同意を得られるよう努力すべきだ。」と書かれている。<台湾に関わる中国の権利主張には歴史的な根拠が全くないから「戦狼外交」を展開する他ない>のである。(資料10参照)
増加する戦狼外交官
産経新聞論説委員兼政治部編集委員の阿比留瑠比氏は、次のように分析する。「戦狼タイプの外交官が近年急速に増えている。習近平政権の強硬な対外路線があり、強気で挑発的な発言をする方が上層部に評価されることが背景にある。これはやがて諫言する者が誰もいなくなる独裁国家の病弊の表れだ。」
王毅外相自らも、「日本の現職の指導者が台湾問題に武力介入を企む誤ったシグナルを公然と発し、言うべきではないことを言った。触れてはならないレッドラインを越えた。」と発言したが、日本通の王氏は日本側の実情を百も承知であり、この発言が習近平主席の歓心を買おうとしたものであることは明らかだ。(産経11月27日紙面)
一方、既に紹介したさまざまな威圧行動が、中国政府の複数の部署からタケノコのように現れてきた現状について、ジャーナリストで雑誌『正論』編集長を務めた桑原聡氏は、「中国外交官の言動は独裁者に対する忠誠の結果であり、怒りよりも哀れさを感じざるを得ない。」と評しているが、本質を突いているのではないか。(資料11参照)
本件に関して注目されるのは、米中首脳会談に出席した中国側の高官の態度について、トランプ大統領が「あんなに怯えた人間を見たことはない」と評したことだ。外交トップの王毅外相を始め米中首脳会談に同席した高官ですらそうであったとしたら、総領事の言動も推して知るべしだ。中国とはそういう国なのだと、認識を新たにせざるを得ない。
中国の常套手段
そもそもこの事件の事の発端となったのは、立憲民主党の岡田克也氏だった。国際情勢が緊迫さを増している状況を踏まえて、「最悪の事態に備えて」台湾有事について政府と野党の間で認識を合わせておきたいという主旨に基づく質疑応答なら理解できるが、単に高市首相の揚げ足取りを狙ったのだとしたら、立憲民主党は国民の信を一層失うに違いない。
桑原氏は、「それにつけても、哀れな中国の役人の言葉に便乗して、もっともらしい理屈をつけて高市首相批判をする政治家、メディア、評論家の何と多いことか。彼らは一体何を守ろうとしているのか。中国の国益?それとも習近平の面子?」と書き込んでいる。(資料11参照)誠にその通りだ。
産経新聞台北支局長の西見由章氏は、中国が戦狼外交に走る歴史的背景について以下のように分析している。(産経11月27日紙面)
「中国の戦略は、孫子兵法等の古代思想やマルクス主義の弁証法的唯物論、及び毛沢東思想が土台になっている。相手が抱える矛盾(内部対立)を利用して分断を図るのは、全ての存在は矛盾を内包すると考えるマルクス主義の弁証法的唯物論の発想に立脚している。」
「さらに相手の選択肢を制限する行動をとり、自らが期待する行動が自然にもたらされる状況を生み出し、機が熟すのを待つ。それは老荘思想の『無為』に通じる。」
高市首相発言を契機に中国政府は前述した制裁措置を矢継ぎ早に発動したが、正にこれは、「日本側に脅しをかけ勢いを生み出し、一触即発の機運を醸成して、野党や経済界、メディア、国民が高市政権を批判するよう仕向けて孤立させ分断を図る」ものであることが明らかだ。
中国側の識者はどう見ているか
上海国際戦略研究所の趙楚副所長は、中国側の日本への抗議の語気は強いが、主に言葉の上に留まっており、実質的な行動はまだ取られていないと分析している。中国は日本とある程度の実質的な関係を維持したいと考えて、行動をエスカレートさせずに今後柔軟に対応できる余地を残している。ただし日中間の「政治的共通基盤」はすでに損なわれた。(資料12参照)
たとえ現在の争いが沈静化したとしても、両国の「負の相互作用をもたらす火種」は依然として存在する。日本は世界の重要な国家として「普通の国」になることを模索しており、中国も超大国の地位を追求しているため、この構造的矛盾は間違いなく両国関係に困難をもたらす。中国の台頭にどう対応するかは日本が直面する重大な課題であり、中国にとっては日本という重要な隣国との関係を如何に適切に処理するかが大きな試練であり、従来の思考や観念はもはや適用できない。(資料12参照)
日本は泰然自若たれ
在日台湾人団体が中心となって複数の在日の団体が連名で共同声明を出して、中国政府による威圧に抗議している。「高市首相の答弁は、日本及び周辺諸国の安全保障に関する仮定の議論の中で発せられた日本政府としての公式見解であり、何ら問題はない。中国が現状の変更を目論んで武力による攻撃を行わなければ、日本が存立危機事態に陥ることはなく、自衛隊を派遣する必要もない。・・・中国はその威圧的な言動を改めなければ、そして国内での人権問題を改善しないなら、今後も地域の最大の不安定要素であり続けるだろう。」(資料10参照)
中国にとっては威圧的言動を改めることも人権問題の解決もできない相談であるから、中国は今後とも地域最大の不安定要素であり続けるだろう。それを前提として日本はどうすべきかを考える必要がある。
小野田紀美経済安全保障担当大臣は、今回の事件に関して、「何か気に入らないことがあったら、すぐに経済的威圧をしてくるところに依存し過ぎることはリスクがある。」と素直な所感を述べているが、誠にその通りである。中国は戦狼外交を展開しているが、世界から見れば小野田大臣が語ったように、中国に対する警戒心と嫌悪感が世界に拡がる結果にしかならない。
中国は経済規模において西側先進国を超えてアメリカと肩を並べるところまできたことは事実である。日本や欧州諸国からみれば、「大国に相応しい品格と作法」を身につけることを期待するのだが、中国の戦狼外交は止まらない。中国が作法を変えることは期待できない。
では日本はどうすればいいのか。元外交官で、キャノングローバル戦略研究所理事・特別顧問の宮家邦彦氏は『中国共産党のトリセツ』と題した興味深い記事を書いている。「5つのトリセツ」は次のとおりであり、誠に言い得て妙という他ない。(資料13)
1.台湾と抗日は最重要問題なので安易に妥協しない
2.メンツが潰れれば制御不能となり、論理が通用しない
3.激高した後、我に返るまでには相当の時間が必要
4.その間、中国側の不利益につき熟考させることが肝要
5.妥協するにもメンツが必要なので、面倒である
中国の作法は今後とも変わらないと仮定した上で、隣国の日本はどう付き合うべきなのか。前述した柯隆氏は次のように述べている。「経済学のゲーム理論的な考えに基づいて今後の選択肢を探ってみる。日本の国力は国際社会でリーダーシップを取れるほど強くない。日本は自らの実力を直視して、グローバル社会のリーダーを目指さずに、如何にして日本の国益を守るかを優先的に考えるべきだ。日米同盟に頼りすぎない主体性のある安全保障戦略を描く必要がある。ここで問われるのは安全保障にかかわる日本の主体性だ。日本は国際社会に貢献することができるが、覇権国家にはなれない。重要なのは日中関係だけでなく、現下の流動的な国際情勢を正しく認識して、日本の取るべき戦略を明確に描くことだ。」誠にこのとおりだと思う。(資料8)
多極化時代における日本の役割
「日本はどうすべきか」という問いは、以下の三つの前提事項を踏まえて考える必要がある。
前提事項1:国家や国際社会に関わる全てのシステムは未完である
前提事項2:アメリカを含め、大国はいつの時代にも強引であり時に傲慢である
前提事項3:アメリカ1強体制から多極化へ、覇権体制が変化しつつある
日米欧諸国は民主主義国家であり、民主主義や資本主義を基幹システムとして成立しているが、中国やロシアは専制主義国家であり、異なる基幹システムの上に構築されている。基幹システムが異なるので価値観を共有することができない。
アメリカを含めて中国とロシアは軍事大国かつ核兵器保有国であり、時に国際社会のルールに従わない強引・傲慢な振る舞いをすることは古今東西変わらない事実である。最近ではプーチン大統領によるウクライナへの軍事侵攻がその典型例であり、習近平主席の戦狼外交も、トランプ大統領のMAGA外交も強引・傲慢という点において本質は変わらない。
世界大戦終結後、国際秩序維持の役割を果たしてきた超大国アメリカの国力は、中国の台頭と相まって相対的に低下してきた。歴史的な動向として俯瞰すれば、大戦後の米ソ冷戦構造→アメリカ一強体制→多極化へと国際秩序の骨組みは変化してきた。現在世界は多極化に向かっているという認識に立って未来を展望すると、中国は地域覇権国を志向しており、日本は米中二大覇権国の間に位置するという地政学的立場から免れることはできない。
前提事項1~2は、それ自体が国際秩序不安定化の原因になり得る。それに加えて現在、「アメリカ1強体制から地域覇権国の並立へ」地政学の基盤が変化しつつある。トランプ大統領がウクライナ戦争など国際社会の問題を、地域の当事国の頭ごなしに、地域覇権国である中露とアメリカで解決しようとすることがその証左である。
この動向を踏まえて考えれば、日本の役割と進路は自ずと明らかになる。ズバリ言えば、三つの前提故に顕在化する諸課題に対し、解決のオプションを提示することにある。何故なら前提事項2及び3は当事国であるが故に覇権国には解決できないものだからだ。
ウクライナ戦争勃発以降、BRICS、グローバル・サウスなどが台頭し、相対的にG7の役割が低下してきた感があるが、前提事項1~3を考えるとき、現在進行中の国際社会の秩序崩壊を立て直す役割は、能力と資質において日本と欧州の他に存在しないことは明らかである。
覇権国を志向する米中露と異なり、日本と欧州は覇権に相応しい国力と資質を備えていない。一方で日本と欧州は、米中露にはない歴史、経験、能力を蓄積している。欧州は理念先行で物事を考え、その理念を世界に強要しようとして世界から嫌われる一面があるものの、前提事項1の多くのシステムを発明したのは欧州である。
一方日本には縄文以来、共生・共存・調和を基本的理念とする独自の文明を育んできたユニークさがある。総じて「地球問題」を解決するアイデアと技術を創造する資質を保有する世界でもユニークな国である。さらに日本は世界最大の債権国である。つまり、文化も技術も資金も持っているのが日本なのであって、欠落しているのはそれを戦略的に使う主体的な意思である。
これら日本が有するポテンシャルを駆使して、戦後80年間米国に従属してきた路線を修正し、前提事項1~3を解決する役割を欧州と協力して担うことこそポスト戦後80年時代の日本の役割であると信じて止まない。
参照資料:
1)中国が「存立危機事態」でブチ切れた「10のお家事情」、近藤大介、現代ビジネス、2025.11.18
2)「可能性」を語ることこそ抑止力、伊藤俊幸、産経正論、2025.11.18
3)習近平国家主席が高市首相に言われ放題、福島香織、JBpress、2025.11.6
4)「存立危機事態になり得る」高市総理答弁に中国猛反発、Abema Times、2025.11.26
5)高市首相の一言に中国が大激怒するワケ、白川司、ダイヤモンド・オンライン、2025.11.26
6)日本外交の舞台裏を抉る!、山上信吾、アサ芸プラス、2025.11.24
7)本当は「高市発言」に頭を抱えていた!、石森巌、アサ芸プラス、2025.11.20
8)日中関係急悪化、よく見てみると結局、高市政権には「危機感は十分だが、戦略がない」というだけのことではないのか、柯隆、現代ビジネス、2025.11.28
9)「高市殺害予告」総領事は革命家?、乾正人、産経、2025.11.21
10)高市首相答弁は何ら問題ない、在日台湾同郷会、日刊スポーツ、2025.11.20
11)怒りより哀れさ感じる忠誠、桑原聡、産経、2025.11.21
12)日中の対立は沈静化するだろうがアジアの構造は既に変化、Record China、2025.11.25
13)中国共産党のトリセツ、宮家邦彦、産経、2025.11.20